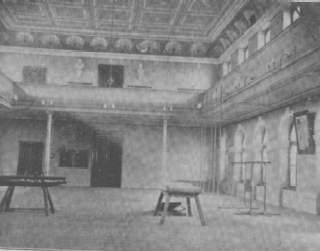10.遠足の「応酬」 --- プラハティツェの場合

北ボヘミアのリベレツ(独語名ライヘンベルク)に建てられたドイツ系体操協会の体育館、1893年8月落成、出典: Die sudetendeutschen Selbstverwaltungskorper: Eine Sammlung von Darstellungen der sudetendeutschen Stadte und Bezirke und ihrer Arbeit in Wirtschaft, Finanzwesen, Hygiene, Sozialpolitik und Technik, Berlin-Friedenau, Vol.1, 1929, p.160. (found at Sudetendeutsches Archiv).
|
1896年4月23日、青年チェコ党のグスタフ・エイム(Gustav Eim)らは帝国議会で政府質問(Interpellation)を行っている。南ボヘミアに本拠を持つソコル・フス地区(Zupa Husova)が、聖霊降臨祭の時期にプラハティツェ(独語名プラハティッツ、地図8)への遠足を計画しているものの、「信頼できる情報」によれば、その申請が却下される見込みだというのである。しかしながら、プラハティツェ住民の四分の一はチェコ人であり、必ずしもドイツ人だけの街というわけではない。しかも、ソコルの遠足は、単にネイションとしての意識(Bewusstsein)を育むことを目的としたものであり、「敵方」が主張するような危険性はありえない。それなのに、遠足を禁止するというのは集会の権利を踏みにじる行為ではないか。エイムたちはこのように主張したのであった。
この件を知って一番驚いたのは、プラハティツェ郡知事(Bezirkshauptmann)だったのかもしれない。4月25日にプラハの総督府に向けて出された報告によれば、彼は、帝国議会で政府質問がなされたことをチェコ系の新聞で初めて知ったのであった。というのも、ソコルの遠足に関わるような申請は、この時点ではまだ提出されていなかったのである。実際に、ソコル・フス地区から遠足の申請が出されたのは、5月3日になってからであった。
5月5日、プラハティツェ郡知事から改めて文書が出されている。当局に提出された申請書によれば、ピーセク(Pisek)に本部を持つソコル・フス地区は、聖霊降臨祭の期間中である5月24日、ユニフォームを着用したメンバーによるフシネツ(Husinec)とプラハティツェへの遠足を予定しているのだという。最初の目的地であるフシネツでは、ヤン・フスの生家での花輪の献呈、および弁士によるスピーチが行われる。
だが、郡知事にしてみれば、このような形の遠足は政治的な示威行為であり、ソコルが掲げている規約にそぐわない行為であった。フシネツでは、近年フスに関わるプロパガンダが盛んであり、ソコルの遠足を認めるとそれを助長する危険があるというのである。郡知事は、同団体によって出された1894年の申請と同様、今回の遠足についても、フシネツ部分へのプログラムは許可することができないと結論づけている。

1881年1月23日に西ボヘミアのカルロヴィ・ヴァリ(独語名カールスバード、地図6)で行われた「夕べの集い」の広告、主催は当地のドイツ系体操協会。内容は、オーケストラの演奏、声楽、器械体操など。出典: Karlsbader Anzeiger, No.3, 1881. (found at SOkA Karlovy Vary).
|
また、ドイツ人が多数を占めるプラハティツェ市内に大量のチェコ人が入り込むようなイヴェントについても、郡知事はこれまで認めてこなかったのであった。全体としてはドイツ人とチェコ人の混住地域であるプラハティツェ郡において、両者の不和を避け、しかも最大限、両者に結社の自由を認めるためには、これは必要不可欠の措置なのであった。したがって、プラハティツェへの遠足も、1894年に出された前回のプログラムと同様、不許可とされるべきであった。
しかも、1896年4月14日 --- したがってソコルよりも前に、プラハティツェの合唱団より申請が出されており、聖霊降臨祭にあたる5月24日と25日、プラハティツェ市内にてプルゼニ(独語名ピルゼン)およびウィーンの合唱団と共同で男声合唱祭(Liedertafelfest)を行う件が、同月23日付けで許可されていたのであった。だが、プラハティツェは古い街であり、中心となるリング広場(Ringplatz)以外にはイヴェントを行う場所もなく、そこに通じる道も路地ばかりであった。たとえ、チェコ人とドイツ人の対立を度外視したとしても、二つのイヴェントを同時に行うのは、郡知事によれば、絶対に不可能であった。
ちなみに、男声合唱祭の日には、会員たちは駅からリング広場までパレードを行い、広場にて市長から歓迎の挨拶を受ける手はずになっていた。その後、午前中いっぱい、広場、および近隣の飲食店(Wirthshauslocalitat)にて祭典が行われるはずであった。
もしもである。この日にソコルの一行がプラハティツェにやって来たらどうなるであろうか? 彼らが目指すであろう当市のソコル協会やチェコ社交クラブ(Beseda)には多人数を収容できるような場所はなく、結局は、リング広場にやって来るしか方法はないはずである。しかも、飲食店の数は極めて限られている。ソコルの一行は、ドイツの旗(*)で染まった街の中を歩き、しかも、広場や飲食店でドイツ人の集団と鉢合わせすることになるだろう。それでも、両者の衝突を防ぐことは可能であろうか?
(注*) 当時のオーストリアにおいて、ドイツ的な色とされていたのは黒・赤・黄であったが、その他にも、オーストリアの色として黒・黄、オーストリア・ドイツの色として赤・白・赤、大ドイツ主義の色として黒・白・赤のパターンなどが使われていたようである。なお、ここで何色の旗が使われていたかについては明示されていない。
しかしながら、と郡知事は続ける。最近になってチェコ人の発言力が増したこと、ネイション同士による対立の増加、テプリツェのソコル祭典に関する一件(第8節参照)といった点を考慮すれば、ソコルの遠足を禁止することが果たして得策なのか、という疑問もある。結局のところ、5月5日付の文書においては、彼は決断を保留し、最終的な決定をプラハのボヘミア総督に委ねたのであった。
この件に関するボヘミア総督の返答については、筆者は発見できていない。が、5月13日にプラハティツェ郡知事が正式にソコルの遠足を不許可としたところを見ると、おそらくは郡知事の意見に同意したのであろう。この日、郡知事は、ボヘミア総督に向けても再度報告書をしたため、遠足を不許可とした理由について詳細に述べている。
その内容については、すでに言及した5月5日付の文書と重複する部分が多いため、ここでは特に説明する必要はないだろう。ただし、この報告では、郡知事自身による推測が二つほど追加されている。一つは、ソコル遠足が、本当に実施するためではなく、男声合唱祭に対抗するためだけに企画されたのではないか、という点。もう一つは、単にプラハティツェの郡庁を威嚇する目的で、ソコル・フス地区から実際に申請が出される前に帝国議会で政府質問がなされたのではないか、という点である。
いずれにせよ、それでおとなしく引き下がるようなソコルではなかった。5月22日には、郡知事の決定を不服としたソコル・フス地区より、ボヘミア総督に対する抗告(Recurs)がなされ、6月2日には青年チェコ党のハーイェク(Hajek)らにより、帝国議会での政府質問が行われたのである。ハーイェクらの主張によれば、偉大な人物であるフスの生家に花を捧げるという行為が政治的な恣意行為と見なされるのは不当であり、ドイツ人側の祭典が行われるという理由でプラハティツェへの遠足が禁止されるのも、結社と集会の権利を踏みにじるものであった。この件に関して、6月10日、ウィーンの内務省よりプラハの総督府に向けて文書が発送され、詳細な報告の提出が指示されたのであった。
ボヘミア総督がウィーンに対してどのようなレポートを書き送ったのかは定かではないが、郡知事の意見を最後まで支持したのは確かなようである。6月24日、彼は、ソコル・フス地区から出された抗告を却下したからである。その後、ソコル・フス地区からウィーンの内務省に向けて再抗告が提出されることはなく、最終的に遠足の不許可が確定したのであった。

中央ボヘミアの都市、プシーブラムに建設されたソコルの体育館<概観>、1903年7月26日落成、出典: Sokol, 31-5, 1905, p.106.
|
19世紀末から第一次大戦までの間に、このような事例がどれくらい発生したのだろうか? 統計的なデータについては、筆者は何も情報を得られていない。だが、少なくとも閲覧することができた公文書から判断する限り、ドイツ人多数地域、あるいは混住地域における役人は、いずれもソコルの遠足に対して強い警戒心を抱いていたようだ。例えば、北ボヘミアのイレムニツェ郡(独語名シュタルケンバッハ)、ヴルフラビー郡(独語名ホーエンエルベ)、トゥルトノフ郡(独語名トラウテナウ)の三知事は揃って、ユニフォームを着た千名のソコル会員がドイツ人地域を通過していくことに極めて強い不安感を抱いたし、西ボヘミアに位置するストゥシーブロ郡(独語名ミーズ)の知事は、プルゼニ・ソコル所属の騎馬隊がドイツ人多数地域を通過してストゥシーブロ郡のホネゾヴィツェ村(独語名ホノジッツ)まで行くと聞いて大いに慌てたのであった(いずれも1897年の出来事)。このホネゾヴィツェ村は、ちょうどドイツ人多数地域とチェコ人多数地域の境目にあたる場所に位置しており、しかも、最近になって村議会の多数がチェコ系からドイツ系に転じ、両者の関係が微妙なものとなっていたところであった。ストゥシーブロ郡知事は、遠足を不許可にしないまでも、もっと「無難な」コースに変更させ、「素晴らしい(phantastische)」ユニフォームを着用させないようにしなければならないと結論づけている。
話をプラハティツェに戻すことにしよう。1914年6月1日、すなわち聖霊降臨祭の月曜日に、ソコルは、1896年の時と同様、フシネツとプラハティツェへの遠足(Ausflug)を企画していたのであった。この件に関して、プラハティツェで発行されているドイツ系の新聞は、「ボヘミアの森の古都、プラハティツェに対するソコルの侵攻」などと書き立て、その一方では、この街に本拠を置くドイツ系の「ボヘミアの森」体操地区(Bohmerwaldturngau)が同じ日に体操祭典を企画し始めたのであった。この地区に所属する18の体操協会がプラハティツェに向けて遠足(Turnfahrt)を行い、リング広場に集結して公開体操を行うというのである。その後、同広場では消防団による模範訓練やコンサート、様々な余興を行い、一種の民族祭典(Volksfest)を現出するという趣向であった。
ところが、である。プラハティツェ郡知事が得た「極秘の情報」によれば、ソコルの「侵攻」が行われない限り、ドイツ人側も祭典を実行するつもりはないというのである。つまり、ドイツ人体操団体から出されたイヴェントの申請は、ソコル遠足を妨害するためだけになされたものであった。同じ日に同じ場所で両ネイションの祭典が行われる場合には、どちらか、あるいは両方を不許可にするという当局のやり方を悪用した一種の戦略である。とはいえ、双方の出方を静観しているわけにもいかず、郡知事は要所要所に警官隊(Gendarmerie)を配置し、「不測の事態」に備えたのであった。プラハの総督府に向けて書かれた文書(5月30日付)の中で、彼は以上のように述べ、当日の状況については電話で逐一報告すると伝えたのである。
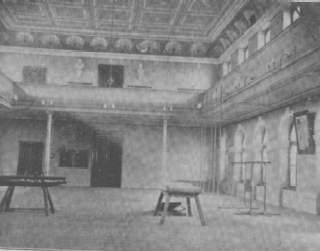
プシーブラムのソコル体育館 <体育室>、出典: Sokol, 31-5, 1905, p.107.
|
だが、結局のところ、チェコ人のソコルもドイツ人の体操団体も、当日は何もしなかったため、郡知事の心配は杞憂に終わったのであった。
1914年に発生したこの事件と1896年の事例を比較してみると、その背景には、いくつかの相違点が潜んでいるように思われる。一つは、ナショナルなイヴェントを不許可にすることがますます困難になりつつあった、という点である。チェコ人とドイツ人の対立が深まるにつれ、地方レベルでのイヴェントを不許可にするという行為に、政治家の、そして世論の注目が集まるようになってしまったのである。実際、1896年にソコルの遠足が不許可扱いにされたことにより、帝国議会では政府質問が飛び、大手の新聞が反応し、そして、プラハティツェの郡知事自身が政治的な対立の渦中に置かれるという事態となった。また、遠足の不許可自体は1896年7月に確定したものの、事後処理をめぐって翌年の97年になってもウィーン、プラハ、プラハティツェの間で書類のやりとりが継続されていたのである。これに対し、1914年に作成された書類においては、--- 明示的ではないものの --- 申請されたイヴェントは原則として許可するというのが前提とされている様子であった。この点は大きな違いであろう。
第二に挙げられるのは、相手方のイヴェントを阻止するために、偽の申請書が頻繁に出されるようになったという点である。この件に関しても、筆者は具体的な数値を挙げることはできない。だが、当局が複数のイヴェントを同時に開催させることに大きな不安を抱いている、という事実に体操団体が気づき、相手方を牽制、又は妨害するために、本気かどうかに関わらず申請書を出してみる、という事例が増えつつあったのではないだろうか。
第三に推測されるのは、警官隊の動員回数が増加しているのではないか、という点である。チェコ人であれドイツ人であれ、どちらの体操団体も、遠足の通過地点、あるいは目的地として混住地域や相手方のネイションが多い地域を好んで選択し、当局の人間を困らせていたのであった。当初は、容易に不許可扱いにできた事例であっても、時の流れと共に許可を出さざるを得ないケースが増え、それに伴って、「不測の事態」が発生する可能性も高まったのではないだろうか。その結果、必然的に警官隊の配置が必要なケースも増加したはずである。
筆者が手にすることのできた公文書は、全体からすれば極めてわずかな量である。以上に掲げた三つの点についても、そこから得られた印象にすぎない。だが、全くの的はずれというわけではないはずである。
引用文献等
-
SUA, PM, 1891-1900, Inv.c.9101, Karton 2522, Sign. 8/5/20/1 (1896/2).
-
Nr. 163 pras., Prachatitz, am 25. April 1896.
-
Nr. 176 pras., Prachatitz, am 5. Mai 1896.
-
Nr. 181 pras., Prachatitz, am 13. Mai 1896.
-
Z. 13083, Prachatitz, am 13. Mai 1896. (Cit. in Sokol, 22-7, p.158, 1896).
-
Nr. 198 pras., Prachatitz, am 22. Mai 1896.
-
3615/ M.I., Wien, am 10. Juni 1896.
-
Nr. 244 pras., Prachatitz, am 23. Juli 1896.
-
SUA, PM, 1891-1900, Inv.c.9101, Karton 2522, Sign. 8/5/20/1 (1897).
-
6142/ M.I., Wien, am 19 Februar 1897.
-
Z. 17763, Starkenbach, am 6. August 1897.
-
Z. 28598, Mies, am 22. September 1897.
-
SUA, PM, 1911-1920, Inv.c.23522, Karton 5334, Sign.8/5/17/85.
-
Nr. 162 pras., Prachatitz, am 30. Mai 1914.
-
Z. 22228, Prachatitz, am 2. Juni 1914.
-
Andreas Luh, Der deutsche Turnverband in der Ersten Tschechoslowakischen Republik: Vom volkischen Vereinsbetrieb zur volkspolitischen Bewegung, Munchen: R. Oldenbourg, 1988.